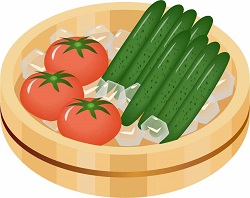
前回、トマトときゅうりの植え付け後、嬉しい着果と初めての収穫のお話しました。
今回は追肥と摘芯、トマトの人口授粉、続く収穫について、お伝えします。
初心者が備忘録的に記しますが、もしお気づきのことがあれば、適宜、ご指導いただければありがたいです。
プレイバック:6月14日 夏すずみ・一番星 それぞれ初めての収穫

きゅうり~追肥
次の機会に書きますが、実は6月14日~16日に5年ぶりに故郷・新潟の実家に帰省しました。
家の前にはテニスコート4面は取れる畑があり、90歳の母が今も野菜を育てています。
流石に全面ではなく、もう一部ですが・・
70年も丹精している母の畑を見て愕然・・自身の駐車場の畑は当然ながらお遊びレベルです(^^;
▼ 6月15日 実家のトマト

▼ 6月15日 実家のきゅうり・母の手入れ


・・母のきゅうりは大きな葉がいっぱい茂り、色も濃い!

だい鉄
かたや、自分のきゅうりの様子です・・

自分のきゅうりはコンテナ栽培なれど、ひょろひょろして葉が少なく、黄ばんでいる・・
支柱の追加や雨よけに気を取られ、植え付けから2週間後にすべく追肥を忘れていたのでした。
弱々しいきゅうりの姿はほぼ肥料切れが原因・・帰省後、すぐにとりかかることにしました。
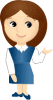 きゅうりの追肥は下記の図書を参考にしました。
きゅうりの追肥は下記の図書を参考にしました。
植え付けの2週間後から2週間おき、(中略)化成肥料30g/㎡を追肥する。出典:藤田智の野菜づくり入門 実業之日本社 2014年12月11日発行 41ページ
コンテナ1つ当たり、10~30gの化成肥料をバラバラとまく。肥料の量はコンテナの容量に応じて加減する。追肥後に水やりすると、肥料が土になじみやすくなる。出典:藤田智の成功するコンテナ菜園 NHK出版 2013年 3月30日発行 20ページ
【6月17日】

1) 中耕
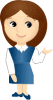 中耕は下記の図書を参考にしました。
中耕は下記の図書を参考にしました。
栽培の途中に、株と株の間や列の間を移植ゴテや小クマデ、手などで浅く耕し、かたくなった土をほぐす作業。排水性や通気性が改善され、根の成長がよくなる。コンテナ栽培では毎日の水やりによって土がかたく締まりがちなので、追肥のたびに行うと効果的。出典:藤田智の成功するコンテナ菜園 NHK出版 2013年 3月30日発行 20ページ
狭いコンテナなので、割りばしで突くように土をほぐせば、根の張り具合を実感します。
なるほど・・土はカチンカチンでした。
2) 夏すずみと一番星、それぞれの株の周辺に化成肥料を30gずつまきます。
リンク

【てしまの化成肥料】 野菜・花全般に使える化成肥料 900g ※代引き不可 追肥に 元肥に 緩効性チッ素 苦土入り トマト ナス ピーマン スイカ メロン キュウリ ゴーヤ トウガラシ ブロッコリー キャベツ カリフラワー

だい鉄
あとで他の本で知ったのですが、株の根元を避け、少し離れた辺りの土中に張っている根を意識してまいた方がよいと。
株の根元に集中させると肥料やけの原因になる場合も・・
株の根元に集中させると肥料やけの原因になる場合も・・
量とまき方に注意が必要です。
3) 培養土を全体に覆いかぶせるように追加します。
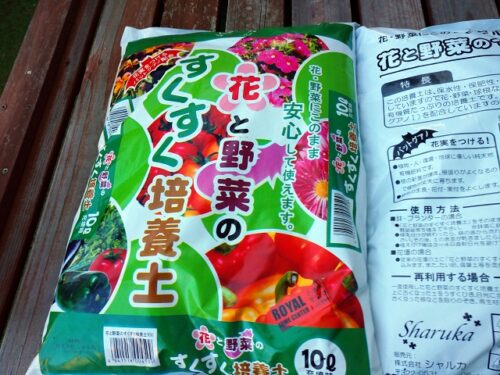


4) そして水やり。
じょうろで2杯半位。プランターの底穴がら水が出るまでたっぷりと。

だい鉄
少しは持ち直してくれるといいが・・
トマト~追肥

トマトも追肥です。
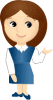 トマトの追肥も前出の図書を参考にしました。
トマトの追肥も前出の図書を参考にしました。
植え付けの1か月後から2週間おきに、化成肥料30g/㎡を追肥する。畝の両側のマルチをめくり、畝の肩の部分に肥料を施す。出典:藤田智の野菜づくり入門 実業之日本社 2014年12月11日発行 13ページ
【6月19日】

他の本には「各株のマルチの穴に化成肥料を追肥」~とあったので、初回は穴の部分にまきました。

が、前述のように”肥料やけ”が心配で、2回目以降は両端のマルチをめくり、畝の肩部分にまきました。

誘引~きゅうり整枝~トマト収穫まで
【6月20日】

きゅうりは追肥が遅れたせいで中々、葉が付かないことが気がかり。左右の株の元気さにも違いが・・
後でより顕著になるのですが、”夏すずみ” は ”一番星” に比べると最後まで弱々しい状態でした。
台木接木の苗であった夏すずみの方が丈夫のはずと考えていましたが・・

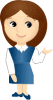 台木接木については下記をご参照ください。
台木接木については下記をご参照ください。
「つぎ木苗」を知る:つぎ木苗とは、病気や害虫に強い野生種や、同じ科のほかの野菜などを台木(土台になる植物体)として、育てたい栽培品種をつぎ合わせた苗のことです。出典:藤田智の成功するコンテナ菜園 NHK出版 2013年 3月30日発行 13ページ

トマトは枝葉が多い、葉が茂り過ぎていることも気になっていました。
【6月21日】
”駐車場の畑” の日当たりについて~日の出からお昼頃までは日向ですが、午後は日陰になります。
トマトやきゅうりは日当たりが大事ですが、半日は日照があるので大丈夫か?と考えました。

この日気付いたこと・・きゅうりのコンテナをトマトの前に置いたため、部分的に日陰が出来ていました。
コンテナの位置をずらしましたが、影になっていたトマトの株はそのせいで他の株に比べ、背が低い状態でした。

ミニトマトはぐんぐん伸び、雨よけ支柱の高さでは間に合わなくなり、雨よけはトマトのみに調整しました。

【6月22日】

この日は風が強く(風速最大5メートル?)、夕方、仕事から帰るときゅうりのコンテナが倒れていました。
コンテナ栽培は背が高くなると不安定になります。倒れにくくなるようコンテナ脇を支柱で調整しました。
【6月25日】
きゅうりもトマトも、ミニトマトも順調に実が付いてきました。



▼ トマトの花の根元近くをトントン指で揺らし、人口授粉です。

▼ きゅうりは根本近くの黄ばんだ葉を落としました。

【6月26日】

この日、トマトの人口授粉にはトマトトーン(着果促進剤)を使いました。
リンク

住友化学園芸 植物成長調整剤 日産トマトトーンスプレー 420mL 関東当日便
▼ 前述の帰省の折、実家の母からトマトトーンを分けてもらい、スプレーに詰め替えて使ったのです。
(やっぱり実家でも使用していたのだな・・)

そして、きゅうりは一番星が収穫できました。

【6月26日】

収穫を終えたら、本格的な整枝です。
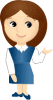 きゅうりの整枝も前出の図書を参考にしました。
きゅうりの整枝も前出の図書を参考にしました。
整枝は3段階で:
つる性のきゅうりは、親づるの葉のつけ根から子づるが伸びて広がります。実のつきをよくするため、生育段階に応じた整枝をします。(以下、下記ご参照)出典:藤田智の野菜づくり入門 実業之日本社 2014年12月11日発行 42~43ページ
1)わき芽かき
下から5節目までのわき芽はすべて手で摘み取り、親づるを伸ばします。
2)子づるの摘芯
子づるが伸びてきたら、子づるの葉1~2枚を残して、その先を切ります。数を抑えて質のよい実をつくり、葉の茂りすぎを抑える効果があります。
3)親づるの摘芯
親づるが支柱の高さに届いたら、先端を摘み取ります。

だい鉄
1) わき芽かき は前回、6月1日に行ったので、
今回は2)子づるの摘芯 と3)親づるの摘芯 の実施です。
今回は2)子づるの摘芯 と3)親づるの摘芯 の実施です。
▼ 親づるの先端を摘芯

▼ 摘芯後の親づる

▼ 楽しみな小さい実も付いています。

摘芯の後は2度目の ”中耕” と ”追肥” を行いました。
夕食には一番星をポリポリ~♪

▼ 帰省のお土産で買ってきた新潟の名物~南蛮味噌を付けて♪


【旨味噌】健次の晩酌味噌セット4 かぐら南蛮×2 にんにく生姜×2 梨蜜 唐辛子 かぐら南蛮 梅酢 醸造酢仕立 ギフト 贈答品 越後亀田郷 村山健次商店 謹製
【6月28日】

トマトとミニトマトも摘芯しました。
枝葉の管理は手が届くところまで。そこから先は潔く切り落とし、栄養分を実に回します。
【6月29日】
また一番星を収穫! きゅうりはなり始めると追いつかないほどです。

【7月1日】

今度は夏すずみを収穫♪



きゅうりには遅れていますが、トマトとミニトマトにも実が。


雨の予報なので雨よけをかけます。ミニトマトは雨よけに収まらない高さです。


風が強くなりそう・・またコンテナた倒れるといけないので、トマトと連結します。


【7月2日】

トマトに2回目の追肥をしました。
【7月5日】

一番星は大きなサイズの6本目を収穫!


摘芯した先端からわき芽も伸びており、小さな新しい実も付いてきました。
一方、夏すずみの方は元気なく、先端の実2本は枯れそうな具合・・

▼ ミニトマトの色づき


初めてのトマトは赤くなったけれど、お尻の方に黒い穴が・・


だい鉄
”尻腐れ果” かも知れません(TT)
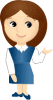 トマトの尻腐れ果については下の図書を確認しました。
トマトの尻腐れ果については下の図書を確認しました。
Q. 実の先端が黒くなる原因は? A. 生理障害で起こる尻腐れ果です。(下記ご参照)出典:おいしく育てる野菜づくり 失敗しないコツと対策 五十嵐透著 ナツメ社 2016年3月8日発行 27ページ
Ca(カルシウム)の欠乏による生理障害です。
Ca欠乏は、土の中のCa成分が不足しているときに起こりますが、他に、土の乾燥によって十分にCaが吸収できない場合や、N(窒素)やK(カリウム)が過剰にあることで、Caが吸収しにくくなり症状が出る場合もあります。
【7月6日】

▼ それでもトマトの初めての収穫です。


そして・・
【7月9日】
きゅうりは相変わらず弱々しいですが、トマトはうっそうと茂っています。


▼ 収穫2個目のトマト・・今度は大丈夫そうです!


▼ 可愛いミニトマトもそろそろ!


だい鉄
併せて嬉しい収穫です~♪

▼ そのまま・・塩で!

次回予告:栽培日誌~収穫!収穫!・・おいしいレシピ
ホントは On time な栽培日誌にしたいと考えてはいましたが、中々そうも行かず・・
とりあえず、毎日のケアを撮影しつつ、記録は追っかけて作成しています。
5時~5時半には起床し、犬の散歩を挟んで畑の様子を見て、適宜、作業します。
仕事前のこの時間はとても静かで夢中の時間・・無になれます。新しい自分の発見です。

毎朝、アシナガバチが朝のご飯を求め、駐車場の畑に30~40分ほど滞在します。
間合いを置けば、彼らも襲ってはこない。お互いの必要を考えながら相対します。
・・いい時間です。
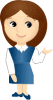 ”駐車場の畑”のシーンを少しコマ送り~ちょっとだけご紹介♪
”駐車場の畑”のシーンを少しコマ送り~ちょっとだけご紹介♪
▼ 7月27日の収穫


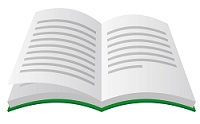
*本文の関係部に記載以外、この記事の作成にあたって、以下の図書を参考にさせていただきました。
【参考図書】
やさしい野菜のつくり方 新星出版社 2007年 3月25日発行
やさしい野菜のつくり方 新星出版社 2007年 3月25日発行






























